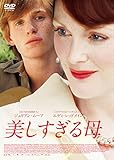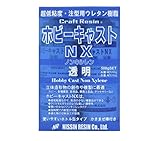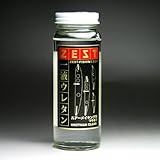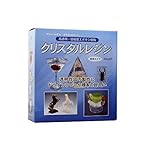レジン(樹脂)とは何か?
スポンサーリンク
ハンドメイドの人気ジャンルの1つに『レジン』があります。レジンを使ったアクセサリー作りは大人気で、以前は『エポキシレジン』が主な材料でしたが、近年はUV(紫外線)によって硬化する『UVレジン』も登場し、たいへんな人気です。
また、模型の世界では、何十年も前から『ウレタンレジン』を使用した作品作りが行われていますね。(かつて、コミックボンボン誌では、ウレタンレジンでブロック(かたまり)を作り、彫刻刀などを使って、そのレジンブロックを彫り、「ガンダム」の頭部を作り出すという、当時の小学生たちを震撼させた作例が載っておりました…。)
基本的に、ハンドメイドや工作に使われるレジンは、硬化性のレジンで、最初は液状で、何らかの刺激をあたえると、硬化して固体になる素材。ある程度、自由に形を作ることができ、素材自体、透明なものが多いので、レジンを使った工作は大人気です。
しかしながら、『レジン』と聞いて、すぐにどんな物なのかをイメージできる方は少なくないでしょう。今回は、そのレジンについて解説したいと思います。(※かなりの長文ですので、興味のある部分から読まれてください!)
目次
- 樹脂とは何か?
- 接着剤も塗料やニスも『レジン』
- 日本を代表する天然樹脂「漆(うるし)」
- 天然樹脂の代表と言えば「琥珀(こはく)」
- 世界初の人工的に作られた樹脂は『セルロイド』
- 世界初の合成樹脂『フェノール樹脂』
- 家庭用で入手可能な成型できる硬化性樹脂の種類は?
- 可塑性の樹脂と硬化性の樹脂
- 硬化性樹脂の硬化する仕組み
樹脂とは何か?
インターネット上で『レジン』を説明する記述をみるたびに、思い悩むことはないでしょうか。
レジンとは『樹脂』のことです。
…と書かれていることが多いのですが、では『樹脂(じゅし)』とは何でしょう?…と。
現代では、レジン(樹脂)と言えば、人工的に、化学的に合成された『合成樹脂(ごうせいじゅし)』を指す言葉として、よく使われていますが、そんな合成樹脂が誕生する以前の人類は、『天然樹脂(てんねんじゅし)』を利用していました。
天然樹脂は、植物由来の成分でできたモノが多かったので、文字通り「樹(き)から出た脂(あぶら)」と書いて『樹脂』です。

また、天然樹脂は、植物由来の樹脂だけでなく、シェラックなどの昆虫の分泌液からできる動物由来の樹脂もあります。
接着剤も塗料やニスも『レジン』
さて、少し話が飛んでしまいますが、接着剤や塗料の話を…。
特に、ハンドメイドでレジンを扱っている方には、あまり意識はされていないかもしれませんが、レジンは「エポキシレジン」や「UVレジン」だけでなく、接着剤や塗料やニスも(硬化性の)『レジン』です。
接着剤や塗料・ニスをイメージしてください。最初は、どんな状態でしょうか?…おそらく「液状」をイメージすると思います。
次に、接着剤や塗料・ニスが時間経過するとどんな状態になるでしょうか?乾燥(もしくは重合反応)によって、硬化・固まることをイメージすると思います。
「エポキシレジン」や「UVレジン」の硬化する過程と同じですね。
以下は、タミヤの塗料なのですが…。

品名に「合成樹脂塗料」と書いてありますね。塗料やニスを持ってらっしゃる方は、確認して頂きたいのですが、おそらく同様に「合成樹脂塗料」と表示されているはずです。これは、家庭用品品質表示法という法律で、表示が義務付けられていますので…。
後述しますが、いわゆる「瞬間接着剤」も、シアノアクリレートを主成分とした(硬化性の)レジン(樹脂)です。
日本を代表する天然樹脂「漆(うるし)」
樹脂を「樹から出た脂」と先ほど書きました。日本を代表する天然のレジンと言えば「漆(うるし)」が有名でしょう。
漆は、漆の木から抽出された樹液で、古来より塗料やニス、接着剤として利用されてきました。現存する最古の漆製品は、縄文時代早期、約7000年前に作られた物だそうです。
漆を塗ることにより、製品の耐久性を向上させたり、光沢や発色をよくしたりと、その耐久度や美しさから、食器をはじめ、家具などのコーティングに古くから使われています。いわゆる天然のレジンコーティングでしょうかね。
また、漆の色は、もともと茶色がかった透明な樹脂ですが、顔料を混ぜた「黒」や「朱」が有名でしょう。特に「漆黒(しっこく)」という表現は、小説や漫画によく登場しますね。漆は、着色した樹脂、『カラーレジン』の代表と言っても過言はないかもしれません。
なお、漆は、昔から「漆かぶれ」などといったアレルギーが存在することが知られていて、重度の漆アレルギーを持つ方は、漆の木の近くを歩いただけでも、アレルギー反応を起こすことがあるそうです。(これも、レジンアレルギーの一種なのかもしれませんね。)
ちなみに、漆を英語では「ラッカー」と呼びます。(たぶん、模型をされる方なら、馴染みのある言葉のはず…。)
天然樹脂の代表と言えば「琥珀(こはく)」
世界的な天然樹脂の代表と言えば「琥珀(こはく)」ではないでしょうか。植物から分泌された樹液が、長い年月をかけ硬化し、宝石となったものです。生物(植物)由来なので、鉱物ではないのですが宝石に分類されています。(ちなみに、同じような生物由来の宝石としては、「真珠」(貝から生成される)が有名でしょう。)

恐竜の血を吸った蚊が、樹液に巻き込まれて、そのまま硬化し琥珀となり、その琥珀から取り出した恐竜の血のDNAを使って、恐竜を現代に復元・蘇生させる…、というのは、大ヒットした映画「ジュラシックパーク」の冒頭のストーリー。
加工食品に虫が入っていたら、異物混入として事件となるケースもありますが、虫入りの琥珀は、たいへん貴重で、「虫入り琥珀」は高値で取引されるそうです。
古来より、宝石として人気の高い琥珀ですが、アジアで最古の琥珀は、北海道で発掘された約1万4千年前の琥珀。文化遺産オンライン上で、その琥珀の画像があります。
現代で見ても、とても美しい発色です。出土された琥珀は、穴が開いていて、装飾品として利用されていたと思われます。
今、「エポキシレジン」や「UVレジン」を使ってのアクセサリー作りが人気となっていますが、その人気の理由は納得です。市販されているレジン(合成樹脂)を使って、レプリカとは言え、簡単に自分だけの「宝石作り」が体験できるのですから。
たぶん、古代にも、レジンアクセサリーのキットが存在していたのならば、古代の人々の間で、レジンアクセサリー作りは大ブームを巻き起こしていたでしょう。
しかも、天然樹脂である琥珀ができるまでには、数千万年から数億年の年月が必要です。琥珀の前段階である「コーパル」ですら、数百万年以上の時間がかかります。
合成樹脂である「エポキシレジン」であれば、通常は、数時間から数日で硬化しますし、「UVレジン」ならば数分から数時間で硬化しますので、とても手軽です。
あと、漆や琥珀だけでなく、「松脂(まつやに)」も天然樹脂の代表格ですが、松脂の話もすると、また長くなるので省略を…。
世界初の人工的に作られた樹脂は『セルロイド』
長らく人類の歴史には、天然の樹脂しか存在しませんでしたが、19世紀に入ると、ついに人工的に樹脂を作り出す技法を編み出します。その流れをみますと…。
1838年に、フランスの化学者であるアンセルム・ペイアンが、植物繊維の主成分である「セルロース」を発見。
1845年に、ドイツ、スイスの化学者クリスチアン・シェーンバインがセルロースに硝酸と硫酸を混ぜた「ニトロセルロース」の開発に成功。
1856年に、イギリスの化学者アレクサンダー・パークスによって、ニトロセルロースと、楠(くすのき)から抽出される樟脳(しょうのう)を合成して、「セルロイド」(※当時は「パークシン」という名称)の開発に成功。
1870年に、アメリカの発明家ジョン・ウェズリー・ハイアットによって、セルロイドの量産化に成功。(「セルロイド」は彼の会社の商標登録。今は普通名称化。)
…という歴史。
当時、ビリヤードの球の材料には、象牙が使われていたそうですが、セルロイドの登場により、セルロイド製のビリヤード球が普及したそうです。
今まで、熱で溶かして型に流し、製品をつくる材料としては、鉄などの金属がありましたが、金属を溶かすには、かなりの高温が必要で、21世紀の現代でも、なかなか手間のかかる作業ですね。
しかしながら、セルロイドは、90℃程度で軟化し、鉄などよりも融点が低く、加工が容易なことから、いろいろな製品に使われる素材になりました。
ちょっと難しい言葉ですが、簡単に形状を変えることができる性質を『可塑性(かそせい)』と呼び、可塑性の物質を指して『プラスチック』と呼びます。
『レジン』という言葉は、『天然樹脂』も『合成樹脂』をも指す言葉なんですが、『プラスチック』は、主に『合成樹脂』を指す言葉になりますね。(この辺が、ややこしいでしょうか…。)
人類が人工的に合成した樹脂としては、セルロイドが初なので、「人類初の合成樹脂はセルロイド」と呼ばれていますが、合成に天然(植物)由来の成分を使っているので、『半合成樹脂』とも呼ばれています。
さて、日本に目を向けると、明治生まれの詩人・童謡作詞家の野口雨情(のぐちうじょう)が、大正時代に発表した童謡『青い眼の人形』では、
青い眼をした
お人形は
アメリカ生れの
セルロイド
…という詩が登場しています。童謡に歌われるほどなので、大正時代には、日本でもセルロイドは広く普及していたのでしょう。
そのセルロイドですが、今ではあまり見かけることはありません。卓球のピンポン玉(ピン球)は、長らくセルロイド製でしたが、国際卓球連盟(ITTF)の意向により、試合球は、ポリエチレンなどの合成樹脂製に置き換えられています。(記事執筆時点では、まだAmazon等にて、セルロイド製のピン球は販売されていますが、数年後にはなくなるかもしれません…。)
ギターやベースのピックくらいでしょうかね。現存する身近なセルロイド製品は…。
なぜセルロイドが、廃れてしまったのか。その原因は、セルロイドの性質にあります。原料となるニトロセルロース自体、火薬に利用される素材なので、セルロイドも可燃性が高く、火災を誘発しやすかったのです。
昔の映画のフィルムは、セルロイド製だったので、映画館での火事が多かったようですし、先ほどの詩にもあったように、人形をはじめ玩具の素材として、セルロイドは多用されていましたので、以下のような悲劇的な事件も起こりました。
日本の都市災害史に残る大火災の一つ。1932年(昭和7年)12月16日午前9時15分頃、4階の玩具売り場で火災が発生。地下2階、地上8階の建物の4階から8階までを全焼して午後12時過ぎに鎮火した。火災による死者が1人、墜落による死者が13人、傷者が67人という、日本初の高層建築物火災となった。
デパートの白木屋を襲った火災。詳細も引用すると…。
当時、白木屋は歳末大売出しとクリスマスセールが重なり、店内は華やかな飾りつけがなされていた。開店前の点検でクリスマスツリーの豆電球の故障を発見し、開店直後に男性社員が修理しようとした時、誤って電線がソケットに触れたためスパークによる火花が飛び散り、クリスマスツリーに着火。火は山積にされたセルロイド人形やおもちゃに燃え移り瞬く間に猛烈な火炎をあげた
現在では、クリスマスツリーの電飾にはLEDが一般的になり、玩具の素材も難燃性の素材が主流になっています。しかしながら、今の視点で考えると、この玩具売り場は、火薬庫のようなものでしょうから、火災の凄まじさは想像を絶するでしょう。
現行の消防法でも、セルロイドは危険物第5類(可燃性固体)に分類され、たとえば20㎏以上の量を保有しようとすると、消防署への届け出が必要になります。(セルロイドほどではないですが、エポキシ樹脂やUVレジンも可燃物なので、火気厳禁!)
ちなみに、セルロイドは、アニメーションの作画に用いる透明シートの素材としても使われていましたので、今でもアニメ業界では「セル画」という言葉が残っているそうです。
世界初の合成樹脂『フェノール樹脂』
セルロイドは、人類史上初の人工的に作られた樹脂ではありましたが、原料が天然由来の成分だったため、「半合成樹脂」と呼ばれています。真の意味で『合成樹脂』として歴史に登場するのは、1907年にアメリカの化学者であるレオ・ヘンドリック・ベークランドにより工業化された『フェノール樹脂』が最初です。
フェノール樹脂は、石炭酸(フェノール)とホルマリンを反応させて合成された樹脂で、ベークランドにより『ベークライト』として商標化。今では、普通名称化しており、『フェノール樹脂』を指す言葉として『ベークライト』は使わています。
趣味の分野で言えば、電子パーツ屋さんに行くと、『ベーク板』という樹脂製の板が販売されていますが、これは『ベークライト(フェノール樹脂)の板』の略称です。電子工作における基板として、今でも使われていますね。
ベークライトを開発したベークランド(ややこしい…!)は「プラスチックの父」と呼ばれ、富と名声を手にします。
これはまったくの余談ですが、このベークランド家には、悲劇的な事件が…。
その悲劇的な実話をベースにして、映画化がされています。
以上が、合成樹脂の歴史の夜明け部分です。
以降、多種多様な合成樹脂が開発され、現在に至ります。
家庭用で入手可能な成型できる硬化性樹脂の種類は?
家庭用で手に入る成型できるレジンをいくつか紹介しましょう。最初は液状ですが、硬化すると固体状になる樹脂としては、以下のようなものがあります。
1.繊維強化樹脂(FRP)
ホームセンターで売っているレジンの代表格でしょうか。あまりホビー用途で使う方は少ないと思いますが…。FRPは、「エフアールピー」と呼びます。後述しますが、2液性のレジンです。
船とかバスタブの材質として有名でしょうかね。個人的な体験だと、自宅の風呂場のリフォームで使いました。
面倒なので、少し多めのFRPをバケツに流し込むと、すごい熱を発してしまい、たいへん焦った記憶があります。やはり2液性のレジンは怖いなと思った瞬間です。(発火しなくてよかった…。)
2.ポリエステル樹脂
これも馴染みのある方は少ないでしょうかね。以下のような標本に使われることが多いです。
こちらも2液性の樹脂で、Amazonでも販売されています。
3.ウレタン樹脂
ハンドメイド分野よりも、プラモデルなどの模型分野でよく使われているでしょうか。
インターネット上では、ウレタン樹脂を「不透明樹脂」として紹介する例が多いのですが、それは顔料や染料を混ぜ、着色させているだけで、ウレタン樹脂も、もともとは透明です。
成型用の素材としては、2液性の樹脂にて販売されることが多いのですが、二液性だけでなく、一液性も存在します。ニスや塗料に多い印象でしょうかね、一液ウレタンは…。
4.シアノアクリレート樹脂
おそらく最も有名な硬化性のレジンかもしれません。いわゆる瞬間接着剤です。一液性の硬化樹脂。
透明な樹脂ですが、模型分野では、色付きの瞬間接着剤がいくつか販売されています。
5.エポキシ樹脂
ハンドメイド分野での透明樹脂の1番手でしょう。逆に、模型分野では、あまり成型に使われる方は少ない印象です。(接着剤用途では、使われることが多いですかね。)
2液性の樹脂で、「クリスタルレジン」や「デブコン」という商品名の製品が有名。
6.紫外線硬化樹脂(UVレジン)
光を浴びると硬化する樹脂(光硬化樹脂)としては、代表的な樹脂でしょう。紫外線(UV)を浴びると硬化する一液性の樹脂です。
近年は、100円ショップでも販売されるようになり、ハンドメイド分野で大人気に。
硬化後の特性が硬質な「ハードタイプ」や、軟質な「ソフトタイプ」、ソフトタイプよりも柔軟性に富むグミのような質感の「グミータイプ」などがあります。
家庭でも入手できる硬化性の樹脂としては、このくらいでしょうかね。
可塑性の樹脂と硬化性の樹脂
樹脂を大きく2つに分類すると、『可塑性の樹脂』と『硬化性の樹脂』にわけられます。
可塑性の樹脂は、種類が非常に多く、ビニールハウスなどの素材の塩化ビニール樹脂や、ペット(PET)ボトルの素材のPET樹脂、プラモデルの素材として活用されるスチロール樹脂などが有名かもしれません。
これらの樹脂は熱によって可塑化する樹脂です。一度、固めても、加熱すると溶け、冷えるとまた硬化します。「おゆまる」と呼ばれるプラスチック製品も、この熱可塑性樹脂の特性を活用した商品でしょう。
食品で言えば、チョコレートのような感じです。型に流して、自在に成型できる点も同じですね。チョコレートの場合、作るのに失敗しても、また加熱すれば再チャレンジできます。
一方、エポキシ樹脂やUVレジンは、硬化性の樹脂です。一度、硬化してしまうと、元には戻りません。
食品で言えば、タマゴ(卵黄と卵白)のような感じです。目玉焼きでも、卵焼きでも、オムレツでもよいのですが、いったん加熱して固まってしまうと、元のタマゴ(卵黄と卵白)に戻ることはありません。
硬化性樹脂の硬化する仕組み
硬化性樹脂には、いくつか硬化する仕組みがあります。
熱によって硬化する樹脂
2液性のエポキシ樹脂やウレタン樹脂が、熱硬化型樹脂の代表格でしょうか。A液とB液を混合し、熱を発生させて硬化するタイプのレジンです。
気温の高い時期だと、硬化スピードが上がります。
光によって硬化する樹脂
光硬化樹脂としては、紫外線(UV)を浴びると硬化するUVレジンが有名でしょう。
紫外線量の多い時期や晴れの日などは、硬化スピードが速いです。
一般的に、あまり馴染みはありませんが、工業用の光硬化樹脂としては他に、電子線(EB)を浴びると硬化するEB硬化性樹脂が存在します。
熱と光によって硬化する樹脂
熱硬化性樹脂と、光硬化性樹脂の組み合わせ、ハイブリット型のレジン。主に工業用ですね。
湿気によって硬化する樹脂
空気中の水分と反応して硬化する樹脂。代表的な湿気硬化型樹脂としては、シアノアクリレート樹脂があります。いわゆる瞬間接着剤。
湿度の高い季節は、硬化スピードが速いです。
開封した瞬間接着剤は、密閉容器に乾燥材を投入して封入すると長持ちします。
他にも、衝撃をあたえると硬化する衝撃硬化型樹脂など、硬化性樹脂は様々です。
以上で、樹脂の説明は終わりにしましょうか。当初は1万字以上でしたが、8400文字くらいまで圧縮しました。ざっくりと『樹脂』のイメージを理解頂けると幸いです。
こういった記事を書くと、語尾を変えるなどして文章を模倣される方がいらっしゃいます。参考にして頂けるのは、非常にありがたいのですが、できればfollow付きのリンクを、この記事に与えて頂けると嬉しいです。