エポキシ樹脂の危険性やレジンアレルギーについて
スポンサーリンク

2013年に書いたレジンを冷凍冷蔵庫で保管すべきでない理由という記事が、最近よくアクセスされているようです。(まとめ記事やSNS等で引用されている様子…。)
ハンドメイド分野において、主に、2液性のエポキシ樹脂による『レジンアレルギー』が問題視されているみたいなので、あらためてレジンの中でも、エポキシ樹脂の危険性を書いてみたいと思います。(ちなみに、2液混合型の樹脂としては、ポリエステル樹脂や、ウレタン樹脂も、エポキシ樹脂と並んでメジャーな存在だと思いますが、その辺りの樹脂の話は、またの機会に…。)
◆ エポキシ樹脂の原料である『BPA(ビスフェノールA)』
レジンを冷凍冷蔵庫で保管すべきでない理由という記事でも言及していますが、エポキシ樹脂の主剤は、『ビスフェノールA』です。
『ビスフェノールA(BisPhenol A)』を略すと『BPA』。
このBPAは、エポキシ樹脂だけでなく、ポリカーボネート樹脂の原料としても知られています。
エポキシ樹脂や、ポリカーボネート樹脂の原料に、なぜBPA(ビスフェノールA)が使われるのか?
1番大きな理由としては、安価ということでしょう。(最近は、高騰傾向とも聞きますが…。)
そして、BPA(ビスフェノールA)を使うと、耐久性が高い。つまり、頑丈・丈夫ということもあると思います。
余談ですけど、昔の樹脂製の洗濯バサミって、日光を浴び続けると、パキパキと折れやすくなかったですか?近年のポリカーボネート製の洗濯バサミの出現によって、あまり折れることは少なくなった気がしますが…。
あとは、BPA(ビスフェノールA)を使うと、「透明度が高い」というのも、好まれる理由かもしれません。
このように、原料としてみると、とても性能の高いBPA(ビスフェノールA)ですが、最近は、健康や環境への悪影響が懸念されています。
◆ 『BPAフリー』は世界的な潮流
「BPAフリー」(「BPA FREE」)という言葉はご存知でしょうか?
原料に『BPA(ビスフェノールA)』を含まない、エポキシ樹脂やポリカーボネート樹脂などの樹脂製品が増えており、それらは、「BPAフリー」の製品として、人気があるようです。
たとえば、amazon.co.jpで、「BPAフリー」を検索すると…。
↓2015年8月22日の検索結果(953件のヒット)。
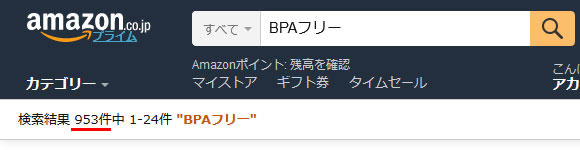
↓2015年10月9日の検索結果(1007件のヒット)。
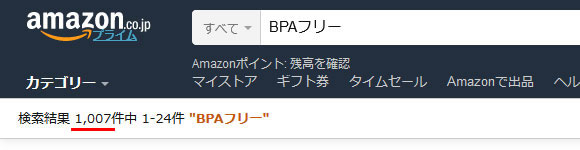
日本でも、BPAフリーの製品は増えているように思えます。
また、以前の記事でも書いてますが、カナダでは、2010年にBPAは有毒と認定し、BPAを含む樹脂製の哺乳瓶の販売は禁止に…。
» 「ビスフェノールA」は有毒 カナダが認定、規制強化へ - 47NEWS(よんななニュース)
その同じ年(2010年)に、フランスでもBPAを含む哺乳瓶の製造・輸出入を禁止する法律を公布しています。
エポキシ樹脂や、ポリカーボネート樹脂から溶け出すBPAが、胎児や乳幼児・妊婦や授乳中の母親に悪影響があるとの懸念から、禁止という強い措置になったようです。
さらに、2011年から「妊婦や親及び子供が食品経由BPA暴露を抑制するためにすぐにできること」というパンフレットを作成・配布するという徹底ぶり。
» フランス厚生・連帯省、ビスフェノールA(BPA)暴露予防策周知のためパンフレットを作成し、配布を開始 - 食品安全委員会
ちなみに、そのフランスですが、2015年1月から、哺乳瓶だけでなく、BPAを含む食品容器も禁止になりました。
» ビスフェノールAを含む食品容器が2015年1月から禁止に-内分泌かく乱物質の規制強化- | 世界のビジネスニュース(通商弘報) - ジェトロ
食品容器以外でも、2014年からEUでは、オモチャに含まれるBPAの規制が強化されています。
» 欧州委員会、玩具中のビスフェノールAを0.1mg/lに規制|環境展望台:国立環境研究所 環境情報メディア
このように、ビスフェノールAを使わない「BPAフリー」の流れは、世界的な潮流と言ってもよいでしょう。
(まぁ、「BPAフリー」だから必ず安全とも言えないんですけどね…。)
» 欧米で回避されるBPA、代替物質も有害? | ナショナルジオグラフィック日本版サイト
◆ 願わくば、正しい知識と対策を
こういった記事を書くと、「『エポキシレジンを使うな!』ということか!」といったご意見を頂くことがあるのですが、その辺りのご判断は、お任せするしかありません。
私としても、最近は少なくなりましたが、注型材料として、エポキシレジンは使ったりしますし、エポキシパテでの造形や、エポキシ接着剤を使用する機会は当然あります。
2液性のエポキシ樹脂の取扱説明書をよく読み、換気の徹底・防毒マスクやゴーグルの装着・素手で触らないように手袋の着用や、衣服につかないようにエプロンの着用などの対策を講じて頂ければ幸いです。
↓私が現在使っている防毒マスクは、以下の防じんマスクとのセット品。
防毒マスクと、防じんマスクの計2個のお得なセットで、防じんマスク用のフィルターも付属しています。しかも、高品質な3M(スリーエム)製です。サイズは、両方ともMサイズで、ほとんどの方は、このサイズで問題ないでしょう。単体で買い揃えるよりも安いと思います。
ただし、防毒マスクは、以下のような吸収缶が必須です。
この吸収缶は、消耗品で価格も高いので、ランニングコストを考えると、吸収缶が安いメーカーのものや、吸収缶を2個取り付けるタイプでなく、1個取り付けるタイプのマスクを選んでも良いかもしれません。(2個タイプの方が性能も良く、呼吸もしやすいのですけども。)
防毒マスクと、防じんマスクについては、機会があれば別途解説したいと思いますね。(完全に蛇足ですが、私の住んでいる田舎は、松くい虫対策などで、ヘリコプターによる薬剤散布が行われる場所なので、こういったマスクの必要性が高いのです…。)
◆ ハンドクリームは有効か?
レジンの硬化中は、目に見えない有毒なガスが発生しています。そのガスから身を守るための、換気であり、防毒マスク着用などの対策なのですが、その対策の1つなのでしょう。皮膚を守るためにハンドクリームや保湿クリームを塗るという方法が紹介されていたりしますね。
皮膚の弱い部分、目の周りや、手首や首などに、保湿クリームを塗って、皮膚を守る・防護するという対策です。
しかしながら、この対策は、逆効果になる可能性もあります。
日本語のネット記事だと、引用元が間違っていたりして、ちょっと信ぴょう性に欠けるので、英文のソースで申し訳ないのですが、以下のような内容が昨年に発表されました。
BPA(ビスフェノールA)は、樹脂製造の原料だけでなく、感熱紙などの顕色剤に使われています。最近のレシートは、感熱タイプが、ほとんどでしょうか。
ハンドクリームなどを塗った手で、これらのレシートに触れると、塗っていない場合と比較して、BPAの皮膚吸収率は、100倍に上がるという衝撃的な内容です。
ハンドクリームなどのスキンケア製品に含まれる油分や、皮膚浸透促進成分が、BPAの吸収率を高めている可能性を指摘しています。
…ということで、個人的には、ハンドクリームや保湿クリームなどを塗るという方法は、あまりオススメしません。
◆ 主剤と硬化剤は、きちんと計量し、よく混ぜる
硬化したプラスチックから溶出されるBPAが問題視される昨今ですが、硬化不良の樹脂は、さらに危険なのは言うまでもないでしょう。
最低でも、0.1グラム単位で計量できるデジタルスケールを使用して、主剤と硬化剤は、比率を守って混合することが大切です。
ミニチュア製作の指南本の中には、エポキシ樹脂の主剤と硬化剤を、爪楊枝で1滴・2滴と垂らして計量する方法が載っていたりしますが、個人的には、まったくオススメできません。
低量だと、計量誤差によって、硬化不良が起きる確率が上がってしまいますから、もったいないかもしれませんが、ある程度の量を使って、硬化不良を防ぐことも重要でしょう。どうせ硬化不良になってしまえば、その分を無駄にしてしまうので。
あと、主剤と硬化剤を、よく混ぜることも大事ですね。
◆ エポキシパテは、指サック着用が便利
模型製作でもメジャーな素材ですが、昨今は、ミニチュア製作でも、エポキシパテの利用を、よく見かけます。正直、ゴム手袋や、ビニール手袋を着用して、エポキシパテをこねたりするのは、やりにくいし、面倒ですよね。しかしながら、素手で触るのは、まったくオススメできません。
特に、エポキシパテは、爪の間に入ると取れにくく、長時間の曝露になってしまい、非常に危険!
エポキシパテの場合は、以下のような指サックを着用すると、手軽な上に安全性も高く、オススメです。

指サック表面のイボイボで、エポキシパテに跡がつくのが嫌な場合は、最初から指サックを裏返して使用しましょう。間違っても、エポパテに触れた面を、裏返して使用してはいけません。防護の意味がありませんから。
指サックは、ダイソーにて10個入りで売られています。サイズは、大・中・小の3種類があったはず…。
(ちなみに、私はセリアで、5個入りの指サックを買った後で、ダイソーの10個入り指サックを見つけました…。)
◆ 作業時は火気厳禁!
これも見落としがちな点かもしれませんが、硬化前のエポキシ樹脂は可燃性が高いので、エポキシ樹脂を取り扱う際は、火気厳禁で!
これは、エポキシ樹脂にかぎらず、可燃性の高い接着剤や塗料などの有機溶剤全般にも言えることでしょうか。
作家の景山民夫さんは、火事でお亡くなりになられていますが、プラモデル用の接着剤の引火が火災原因として、模型製作者の間では、知られていますね。
◆ レジンアレルギー
これもエポキシ樹脂に限りませんが、1度、樹脂アレルギーを獲得してしまうと、硬化後の樹脂に触れるだけでも、アレルギー反応を起こすことがあります。
レジンアレルギーを引き起こすには、個人差が大きいので、曝露量を減らす、曝露時間を減らす努力が必要かしれません。(要するに、エポキシレジンの取扱量を減らしたり、作業時間の短縮や、取り扱う間隔を空けるようにすること。)
花粉症のように、今まで大丈夫だった方も、突然発症するケースがあるのがアレルギーの怖さです。
レジンアレルギーになってしまうと、虫歯治療でのレジン充填(いわゆる樹脂の詰め物)ができなくなったりと、弊害も大きいので、硬化前や硬化中のレジンを素手で触ったりされている方は、今一度、考えて頂きたいと願っています。
◆ 他にも対策はいろいろ
細かいことかもしれませんが、レジンを扱った手で、米を研いだりするのもオススメできません。レジンだけでなく、よく塗料や接着剤などを使用される方は、こういった場合、米を研ぐ器具を利用したり、『無洗米』を活用したりと、対策する必要があるでしょう。お米を研ぐ器具は、最近は100円ショップでも目にしますので、この辺りの対策もご検討ください。

